ヘルプマン
2013.09.29 UP
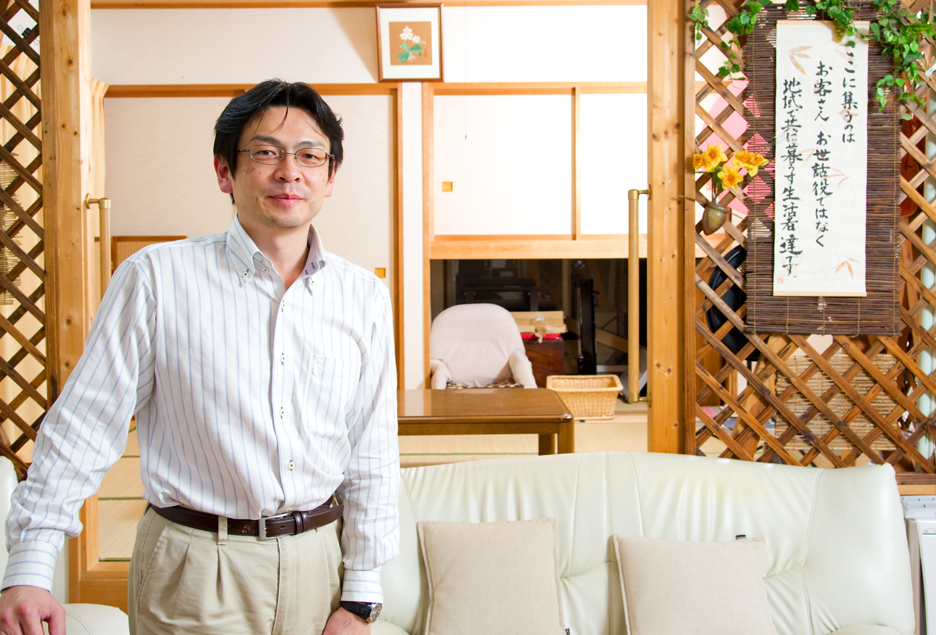
郷里の栃木県佐野市でNPO法人「風の詩」を設立した永島徹さんは、地域のなかを縦横無尽に活動する独立系の社会福祉士(ソーシャルワーカー)です。ソーシャルワーカーというと、日本ではあまりなじみがないかもしれませんが、欧米では、地域基盤を持ちながら社会の課題を解決する人として知られる存在。大学での実践研究活動にも参加し、現場の実態をアカデミックな場へも届けています。 (※この記事は2012年以前のもので、個人の所属・仕事内容などは現在と異なる場合があります)
ソーシャルワーカーとは?
一般にソーシャルワーカーといえば、社会福祉士のこと。介護保険法やさまざまな社会福祉法などの領域で、福祉総合相談や各種制度を活用した、生活支援を行う人のことを指します。約20年前に国家資格になりました。
自治体や病院で働くケースと個人で経営するケースがありますが、僕の中ではソーシャルワーカーはもう少し広い概念。例えば欧米では大学院でソーシャルワーカーの修士号を取得して、地域基盤を持ちながら社会の課題を解決する人として認知も高い。国際ソーシャルワーカー協会があるほどインターナショナルな存在なんです。
ただ、残念ながらまだ日本では「ソーシャルワーカー?何それ?」という現状で認知度が低いですね。
僕がソーシャルワーカーを選んだ理由
僕がソーシャルワーカーをめざそうと決心をする、ひとつのターニングポイントとなったのは、高校時代の友人の死でした。
友人は優等生で、将来は順調に優秀な仕事をしていく道を歩んでいくことだろうと思う子でしたが、心身的に患っていたことを知り、やっと会えたときは、二度と語り合えない永遠の眠りについていたのです。その友人の最期に会ったとき、「ここまで人は変わってしまうのか」という状態でとてもショックを受けました。まだ多感な時期ですから「自分にもできることがあったはずなのに」と出口を求めていました。
そんな時に図書館でたまたま出会ったのが『医療ソーシャルワーク』(誠信書房 中島さつき著)という本。そこで「こんな形で人の役に立つ方法があったんだ」と気づきがあり、さらに実際の大学病院で実践をしているソーシャルワーカーにも会って、何となく将来の方向性が見えた気がしました。気がつくと親の心配をよそに、福祉系の大学への進学を決めていました。卒業後は精神科ソーシャルワーカーとして精神障害回復者の社会復帰活動に従事しその後、地元栃木県に戻ってからは、在宅介護支援センターでケアマネジャーとして活動してきました。
地域と奏でる「風の詩」
2003年に「風の詩」を設立しました。当時、地域の認知症の実態を調べていたところ、「このままいくと施設も病院もいっぱいになる。自分たちの地域づくりをしていかないとどんなシステムを作っても間に合わなくなる」というあせりを感じました。それまで在宅介護支援センターでケアマネジャーをしながら地域と関わってきたのですが、動けば動くほど、制度政策の縦割りの壁にぶつかり、閉塞感を感じていました。
そこで自分の国家資格を活かして、地域の中を縦横無尽に動けるソーシャルワークができる社会福祉士事務所を始めることを決意しました。お金も場所もなかったので、3階建ての自宅の1階を認知症のデイサービス、2階をケアプランセンター兼社会福祉士事務所、3階を自宅として活動を始めました。
「ヘルプマン!」の仁とソーシャルワーク
漫画「ヘルプマン!」では介護士の百太郎が痛快に現場であばれて、仁が「世の中そううまくいかないんだぜ」って言いながら、社会的な制度を使いこなして百太郎を援護する社会福祉士の役割を果たしています。そんなふうにソーシャルワークとケアワークは、一体化していく部分があると考えています。介護現場で行われているケアワークに、対人援助的なソーシャルワークを加味しないと本当の意味での生活のお手伝いをさせていただくことにはなりません。「生活」であるものが「作業」という機械的なことになってしまうとどうなるか。
例えばお風呂での入浴介助の際、わずか約30分で50人入浴させたら「すごい」とほめられ得意になったりしますが、下手をすると「介護」が「作業」になっていることに気づかず満足してしまいがちです。速くできる事を否定しているわけではありません。限られた時間とマンパワーで日々の業務に取り組んでいる現状の中で、目の前の相手と合意の元に、生活支援である「介護」をしていくことを忘れてはならないのです。
だから「風の詩」では、お客さんとお世話役という関係じゃなく、全員が同じ地域で暮らす生活者であるというのが基本的な考え方です。
これからの認知症ケア
これからの介護を考える時、認知症ケアは非常に大きな社会的課題です。記憶障害など中核症状から幻覚・妄想、徘徊などさまざまな周辺症状(BPSD)を示しやすくなってしまう「認知症」は、20年後には300万人を突破するとも言われています。
認知症ケアにおいて、相手の思いに寄り添った関係性を活かした関わりをしていかないと介護する側、される側ともダメージが大きく、暴力や身体的拘束などの虐待になってしまうことも少なくありません。
実際に僕が在宅介護支援センターで働いていた頃、認知症の姑と介護する嫁という関係の2人が苛酷な介護生活を経て、3ヵ月の間に2人とも亡くなられた例を目の当たりにした時には、表面的な相談だけで判断しサービスにつなげるだけでは根本的な支援にならないと思い知らされました。これまでの「認知症ケア」は、直接的な介護の方法論に重点をおいて考えられてきました。このためどうしても症状への対処法に偏ってしまい、本人の存在・思いが忘れられがちでした。
しかし、これからの認知症ケアは、住み慣れた地域社会で生活していくための支援という視点が欠かせません。認知症の本人、その家族、その人が暮らすなじみある地域社会を視野に入れた、支援のあり方を考える必要があります。認知症ケアこそ、私がソーシャルワーカーとして真価を発揮できるステージであり、生涯かけて取り組むテーマだったのです。
生活環境で人は変わる
要介護認定は、介護の必要度の低い順に1→5と認定されますが、「風の詩」にやって来る人の要介護レベルは平均3.75です。要介護5の人も多く来てくれています。要介護5とは手厚い介護を要する人で、生活の全般にわたって全面的な介護が必要とされている状態です。
以前、社会福祉士の資格取得のための現場実習でここに来た公務員の方が、開口一番、「要介護5の人は寝たきりが当たり前。ここに来るわけがない。それは判定が間違っている!」と首をひねっていましたが、同じ要介護5であっても、家族、地域、専門職、医療保険、福祉などいろんな人たちが本人のなじみある生活背景のプロフィールを共有し、同じ方向で見守りやさしく声をかけ関わりあいをしていくと、認知症が進んだふうには見えません。穏やかに老いていくように見えてきます。
僕が大学院に通う理由
2009年から、日本社会事業大学大学院博士後期課程で実践研究活動を始めました。始めた理由のひとつは研究者の方々と共通言語を持ちながら、情報交換できる力を身につけたいと思ったから。研究者は世の中の現象を理論化し伝えてくれます。
認知症についても本やマニュアルがいっぱい出て来ています。けれども、それが現場に活かされない限りは意味がない。現場で文句をつぶやいていてもしょうがないから、まずは渦中に飛び込んでみようと。研究者らは政策の基になる材料をつくったり、教科書をつくったりしている人たち。僕はあくまで実践者的な立場から現場の状況をまとめて伝えていきます。今の研究で指導してくれる諸先生方には、データを丁寧に汲み取ってもらい、そこに魂を込めるべく熱い議論を重ねています。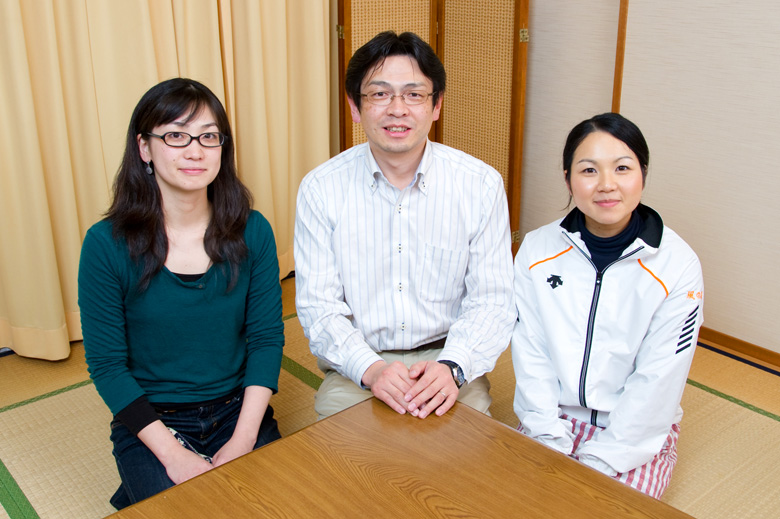
「生活(いき)る」を見守る仕事
僕がケアマネジャーを担当した方々は、自宅で最期を看取るケースが比較的多かったと思います。このことが出来るのは、ご本人の思いとご家族の思い両方を尊重し、意思確認ができていることがまず前提です。それから、ご本人を中心にしてご家族と医療機関、看護師、介護職などがうまく連携して24時間体制で対応できる状態になっているので、万が一、僕がいなくても物事が動いていくようになっています。
これは専門職として大事なことで、自分がいないと動かないようなシステムは、ソーシャルワーカーとして構築してはならないと思っています。逆説的ですが、自分抜きでも機能するように関わっていくことこそがソーシャルワークです。看取る場合も私たちはご家族の後方でそっと見守るというのが基本です。
ただ肉体的に生きるだけでなく、また、精神的に生きるだけでもなく、その人の生活全体を自らの意志と思いで生きることが「生活る(いきる)」ということ。介護とはまさに「生活る(いきる)こと支援」でなければならないのです。
「風の詩」には現場実習などで若い人たちも多く訪れます。そのパワーに触れるたびに、ソーシャルワーカーを志した頃の自分を思い起こします。ソーシャルワークや社会貢献について興味がある方なら、きっと手ごたえを感じられる仕事がここにあると思います。ぜひ、介護業界の門を叩いてみてください。そして、ともに築いていきましょう。一人ひとりが価値ある輝きを放ちながら、生活る(いきる)ことのできる未来を!
【文: 高山 淳 写真: 山田 彰一】
